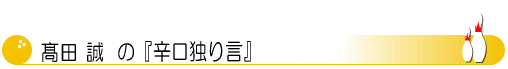
このごろ、ふと時間が有ると5年前の3月11日、あの地震時、盛岡の手前20キロの高速自動車道を片井文乃プロと仕事のため盛岡に向かって高速で走っていましたが奇跡的に無事だったこと。
その片井文乃プロもすでに2人の子供の親となりテキサスで幸せに暮らしている。
地震のため盛岡のホテルロビーの床に毛布1枚を借りて2晩寝たこと。行列をして雑炊の配給を受けたこと。
盛岡のボウリング仲間が炊き出ししてくれたことなどを想い浮かべます。
海軍の街佐世保に生まれた小生は、
小学校の頃より『 わが征(ゆ)く道 』として
戸尾小学校、途中で戸尾国民学校初等科に変名⇒佐世保中学⇒海軍兵学校⇒戦闘機のり というコースを子供ながらに肝に銘じていました。
昭和20年4月1日米軍沖縄上陸 6月12日沖縄陥落
昭和20年6月28日午後11時58分 B29 30機飛来により佐世保空襲
それから 終戦 戦後と小生にとっての人生の大きな目標であった、海軍兵学校に進むという夢が瓦解してしまいました。その後何度か江田島の海軍兵学校跡には行ってみました。
小浦には父の本家が病院を開業していました。
疎開した2週間後の『 昭和20年6月28日 佐世保の家が空襲で焼けた 』と 疎開先でその情報を得たのは空襲の2日後だったと思います。
長兄は海軍兵学校に入学(77期)して留守でしたが、子供ながらに佐世保に住んでいる両親や次兄が(学徒動員)食べるものに困っているだろうと考えての行動だったと思います。
子供用の切符を買い乗り込んだ松浦線が空襲のために北佐世保から先は不通のため北佐世保駅から歩かざるをえませんでした。(不通区間の切符の払い戻しを受けた記憶はありません)。小学3年の子供ですから八幡様より北佐世保駅寄りは1人では行ったことがなく道不案内でしたが、八幡神社はおくんちの時にお参りしたことがありました。
とにかく『 八幡様まで行けば何とかなる 』と思いやっと八幡様の境内に辿り着いたら茶店は消失、境内には焼夷弾の6角形の筒がたくさん落ちていたのを思い出します。茶屋の焼死体もまだ片付けられていませんでした。
ヤットの思いで焼け野原になってしまった市役所方面から現在の上京町に辿り着きました。
半焼の家に辿り着いた時、ふりかえって見たら2キロ離れた玉屋デパートのの建物の残骸の次に見えたのは焼けた弥生座と市役所と公会堂の残骸でした。
私の家が境目で隣の松月堂から佐世保駅方面は焼けていませんでした。
ヤット家に辿り着き、両親・学徒動員の次兄が無事だったことを確認できて心から嬉しかったことを覚えています。
お金も持っていない10才の子供が食料を担いで歩いてくるなど予想もしていなかった父母はきっと喜んだと思います。
昔の子供は自立心が旺盛だったのでしょうね。
その夜は半分焼けてしまいジメジメした床の上に親子4人で寄り添って寝ました。夏なのに、ぬれて生乾きの布団が冷たかった感触が70年たった今でも体に残っています。家が焼けて不幸なはずなのに何故かこの夜はすごく幸せだったことを思い出します。
翌日、まだ空襲の危険がある佐世保からおばあちゃんたちと妹弟の待つ疎開先の佐々町小浦に、佐世保に焼け残っていた柱時計を背中にくくりつけて、父母と別れなければならない悲しさの涙をこらえながら1人で帰りました。 父母と別れるのがさびしかった。
しかし『タダイマ』と疎開先の家に帰りついた時、手編みの藁ぞうりを履いた妹の章子と篤の嬉しそうな顔を見て、『 この2人は俺が守ってやらなければ 』と小学校3年生ながら心に誓ったことを今でも覚えています。
向こう意気が荒く、喧嘩ばかりしていたのはそのせいかも知れません。
あれから70年、残念ながら長兄と妹弟3人とも私より先に天国に行きました。2人は仲が良かったからキット天国で再会して、楽しく昔話をしていることでしょう。今頃2人は、旭中学時代からは野球ばかりやっていて、余り遊んでやらなかった私の悪口を言っているかも知れません。
それもいいでしょう。かわいい妹と弟でした。
終戦後、食べるものが不足していた頃、1日にピーナッツ7粒を食べれば栄養失調にはならないと言われていました。こんなわけでピーナッツや芋アメには、食べるものが不足していた時代の懐かしくも、もの悲しい想い出が一杯あります。昔は南京豆と呼びました。
芋アメのことを芋チョロキンと呼んでいたのは我が家の方言だったのでしょうか・・・?
その後も波乱万丈の人生ではありましたが、とにもかくにも平和で、欲しい物は何でも簡単に手入る時代になり、多少は周りの人たちの力になってあげられるようになった今、
フーットひと息ついて、日本茶でも飲みながら昔の日本を考えることは良いことかも知れません。小生はピーナッツを食べるたび毎に何故か昔を思い出します。
80歳になった現在、
日本オリンピック委員会強化コーチとして研鑽はまだまだ続けてゆくつもりですが、
『 いつまでも元気に長生きするための知恵を考えるより 』
『 いかにスマートに死を迎えるか 』ということの方が大事になってきたような気がします。
とは言うものの
『 やっぱり元気でいなくては上手に死は迎えられないだろうな 』という矛盾も感じる今この頃です。
『 老いてもなお成長を続けたい!! 』
やせ我慢と言う男の美学を貫きながら生きて行きたい ものです。
昔話をする仲間も1人、また一人と天国に行ってしまいます。
苦しかったボウリング不況をともに耐え抜いてきた戦友も少なくなりました。
前頭葉が正常な限り。健康でいる限り、後輩達に技術の伝承を続け、ジュニアたちには大きな夢を持たせ続けたいと思っています。
みなさんどうぞ遊びに来てください、熱くボウリングを語りあいましょう。
過去の独り言はこちらから