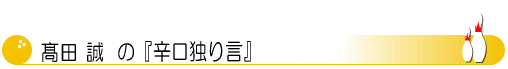
古い資料の整理をしていたら、21年前の原稿が出てきた。
21年前に頭を置き換えて読んでみると、現在と将来に関してなかなか面白いことを言っていると感じる。1995年代の昔話として読んでみてください。
野茂のボールスピードは…?
ボウリングボールのスピードは…?
カール・ルイスのスピードは…?
1995年9月15日のTOTOスーパー陸上100メートルは、リンフォード・クリスティーが10秒フラットで優勝した。
現在100メートルの世界記録1994年7月3日にスイスのローザンヌでバレルが記録した9.85秒である。
先年、東京で開かれた第3回世界陸上選手権大会の100メートルレースでは、カール・ルイスは9.86秒という当時の世界記録を樹立して世界の人々の期待に応えてくれた。しかしながら、一部では大会前から、この大会の開かれる国立競技場のトラックは、新記録が生まれるように『硬く』造られていると言う噂があった。
前記のクリスティーは、決勝の100メートルを10秒フラット、歩数で44.5歩で走っていた。第3回世界陸上選手権大会が開催される以前の大会では、カール・ルイスもやはり100メートルを44.5歩で走っていた。
だがこの第3回大会のビデオを何回見直しても43.5歩で走っている。
この1歩の減少は何が原因であったのだろうか・・・? と考えざるをえない。
さらに、カール・ルイス選手のレース用のシューズがソウルオリンピックの時の165グラムより数グラム軽く作られていたと云う話もあり得ない話ではない。
もちろんそうであるからと言って、カール・ルイス選手が偉大なランナーでないなどというつもりは毛頭ない。
彼は世界のスポーツ史に残る偉大なアスリートである。
ただ、ここで考えたいのは、新記録樹立のための人為的・人工的な条件整備と研究が行われていたと云うことであり、100メートルレースだけでなく、第3回大会だけでもなくボウリングに於けるボールやレーンコンディション、さらには投球時に使用する器具類もスポーツの歴史や記録や技能向上のために人為化・人工化を進めてきた歴史と言ってもよいのではないかと云うことである。
スパイクシューズはそれを象徴する用具と言ってもよく、あのブブカが使う
棒高跳びのグラスファイバー製ポールも、体操競技の鉄棒や野球のバット、もちろんボウリングのボールも、さらにはトレーニングの方法や記録の測定方法(レーン・コンディション)も,これらのすべてが人為化・人工化を進めてきた結果として我々の目の前にあり、それがさらに進められようとしていることである。
このような変化が、その結果としてどのようなスポーツを出現させるのかと云うことについては、とりあえず今は不明としか言いようがないが、しかしそれが人間の自然をも侵しかねないということは述べておかなければならないことである。
ボウリング・ボールについても、これをスポーツという観点から見ると、もう行き着く所まで来てしまっているという警鐘を鳴らさざるを得ない。
しかし、それでもなお世界の人々がその虚構性を知りながらもスポーツの継承と発展に努力し力を尽くしてきたのは、第1に仲間と共にスポーツをする喜びや楽しみを大切にしたいと思ってきたからであり、第2にはスポーツは人間の可能性を開き、伸ばしてくれると考えたからであり、そして第3にそれぞれの時代や社会、民族や階級が求めている人間を育成する機能を持っていると考えてきたからである。(これが学校体育の始まり)
子供たちにとって運動会は楽しい行事であるが、しかしその中で必ずビリになる子供がでるということを知りながらも、なお、カケッコ競争を永く続けてきたのは、ビリの悲しさや悔しさに耐え、それを越えてたくましく生きて行ける子供を育てることが必要かつ重要であると考えられてきたからである。
スポーツはこのような期待と信頼を担って今日まで続けられ、発展してきたと言ってもよい。
だが近年に至って、このような期待と信頼にかげりが生じてきたように思われる。わかりやすいところでは、学生・生徒が運動部への入部を避けて同好会を選択し始めているということ、あるいは競技会での勝利の名誉はほしいが、努力はいやだと云う風潮である。
甲子園で活躍した高校球児でさえも先輩後輩の縦社会、規則づくめで縛られる生活は真向から嫌う。それでいてスポーツは大好き、試合は楽しみたい、そんな学生達に今モテモテなのが『〇〇クラブ』 『□□愛好会』 と云う組織だ。
好きな者同士が集まり、楽しく練習、強制は無いというスタイルだ。
このような傾向の背後には、第1に近年ほとんどのスポーツ競技で世界新記録が出にくくなった。誰の眼にも記録の限界が近づきつつあることは明らかである。つまり、どんなに努力しても新記録を樹立することは困難であることが実感され始めたということである。
スポーツによって得られる社会的栄光と物質的利益が極めて遠い存在になったということである。(このことはスポーツ選手のプロ化を促進している)
そうであれば、プロを目指して努力をして来た超人的な選手達の高度なパフォーマンスをショーあるいは見世物として『見る』楽しみ方を選択する方が賢明と考えるのも今日の若者にとって当然のことと言ってもよいであろう。
人間はおそらく100メートを5秒で走ることは出来ず、42.195キロを1時間で走ることもできないだろう。ボウリングに於いても300AVGを維持することは不可能である。このことは人為化・人工化がなお進むとしても、いずれ人類最後の最高記録が記録される日が来るということである。
その時そのスポーツがどうなるかは、ひとつのサンプルとして、京都の三十三間堂で行われていた『通し矢』が、紀州藩の和佐大八郎によって1686年に達成された8.133本という偉大な最高記録が生まれてから次第に衰え、その後は儀式化していったという事実によって示されている。今日の我々には、一般的スポーツやボウリングを『通し矢』のような運命をたどらせるのか、それとも人間が享受すべき価値あるスボーツ文化へと発展させていくのかという課題がつきつけられており、それは我々が人為化・人工化をどのように考えるのかということと無関係ではないという気がしてならない。
21年前に心配していたことが近年ボウリング界でも発生した。
USBCに公認されていながら、ルール違反のボールが製造販売されたことである。
ボールメーカーが、よりパフォーマンスの強いボール、より売れるボールを作りたかった結果なのであろう。しかしルール違反はルール違反である。
スポーツ・アスリートとして、スポーツ機能や筋力強化もしないで、その日のコンディションにうまく合うボールを持ちこんだ人や、いろいろな器具をうまく使った人が勝ってしまったり、上位にランクされるようになってしまった現在のボウリングは、果たしてこのまま進化していっていいのだろうか・・・・・?
単なるタマコロガシ、単なる遊びとして儀式化してしまわないだろうか。
もちろん、レジャー・スポーツとして楽しんでもらうことはいいことてである、家族の皆さんで大いに楽しんでもらいたい。
しかし、60年間ボウリングをスポーツとしてとらえてきた小生は、用具の進化が過ぎて、スポーツの部分が欠落してしまうのではないかと危惧している。
我々ボウラーは、ボール・パフォーマンスやレーン・コンディションのことばかりに気を取られないで、努力して、今までできなかったことができるようになるスポーツの楽しさ、強くなる努力の楽しさ、質の良い練習をすることも考えてみよう。
本来ボウリングは、1球ごとに変化してゆくレーンコンディションに対して、どう対処してゆくかというスポーツ技能を競うスポーツのはずだ。
負けたことをボールやレーンコンディションだけのせいにするのには納得がゆかない。スポーツは勝った奴が強いのだ。
上達の手段の一つとして、チームリーグに参加し、毎週1ピンづつてもAVGを上げてゆこうと努力することは、いろんな意味でこれらの条件を満たしてくれるはずだ。
チームリーグのすばらしさについては、私のブログ『髙田誠の辛口独り言』の
No.5からNo.8をぜひ読んでいただきたい。
TEAM TAKADA ボウリング練習会は19年間の歴史に終止符を打ちましたが、小生まだまだスポーツ・ボウリングに燃えています。
どうぞ、プロショップに遊びに来てください。待っています。
過去の独り言はこちらから