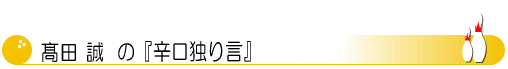
指導者はもちろん選手強化には最低4年間は必要だ、
指導者を志す方々に参考になればと思い、今後数回指導論を掲載したい。
【スポーツは続けなければ上達しない】
コーチの仕事は、先ずボウリングの楽しさと奥行きを指導して、ジュニア達にボウリングを好きにさせるところからスタートしよう。
●対象アスリート別の指導者の分類
【商業地区のインストラクター】
一般の商業施設(ボウリングセンター)に於いて、不特定多数の来場者を楽しませながら、ボウリング愛好者の 開発・育成・指導・マニア化・リーグへの導入・展開などを主たる目的として、施設内で活躍する人たち。
【商業地区のコーチング・スタッフ】
中級レベルもしくはそれ以上に上達したボウラーに対して、個人個人の個性や能力(来場頻度を含む)に応じて、より専門的にコーチを行うスタッフ。
【有資格者の専門コーチ】
特定の個人または少人数のアスリート達をチャンピオンに仕上げると云う明確な目的を持ち、正しく学んだコーチング学をベースに、子供たちの身体づくり、スポーツ学・一般教養・スポーツマンとしてのマナーなど全般にわたり、ある時は寝食をともにしながら、継続的一貫指導のもとに指導して行くコーチの専門家。コーチのプロ。
●日本の子供たちはスポーツを通じて、もっと明るく 楽しく 健康に育たなければならない
【医療費に金をかけるより、健康維持に投資しよう】
日本人は、もっともっと健康になるべきだ。
日本人は学校を卒業すると運動をしなくなる。楽しみながら健康になろう。
●ボウリングを通じて道徳とマナーを指導する
【ボウリングは、ゲームを通じてマナーや道徳を無理なく理解させられる】
アメリカやヨーロッパのジュニア教育は、楽しませながら人間教育。
強ければすべてが許される時代は終わった。
ゴルフ 石川 遼 テニス 錦織 圭 水泳 北島 康介
●日本のスポーツ歴史と学校体育の問題点
【継続的一貫指導の重要性】
柔道・剣道・合気道・弓道 などなど、古来からある日本のスポーツの殆どは個人戦が競技の基本であった。日本では、同じ動きを集団でする習慣が無かった為に、明治時代に入り 富国強兵の必要性から ⇒ 学校に体育と云う時間を作り、ラジオ体操を指導することで、命令の一声で、多数の人間を同時に同じ動きをさせようとする軍隊の動きの基本を指導して来た。この形が日本の学校スポーツにいまだに引き継がれている。
そもそもアソビからスタートをすべきスポーツを学校体育として学校の体育の時間に求めたところから、日本のスポーツは欧米のスポーツとは異なった道を歩き始めた。
日本の学校スポーツは、小学校⇒中学校⇒高校⇒大学⇒社会人⇒プロ と年齢的成長をする毎に、監督やコーチが変わる為に、同じコーチからの継続的一貫指導が受けられず、進級する毎に異なったトレーニングを初めからやり直さなければならない云う大きな矛盾があった。
現在のアメリカの子供たちは、放課後に自分の住んでいる街のスポーツクラブで熟練のコーチによる一貫指導でスポーツを楽しんでいる。
SPORTの語源 DIS-PORT
港から船をときはなす 出港する・楽しむ・遊ぶと言う意味
スポーツの原点は遊びからスタート
●アンダー・ジュニア育成システムを構築する必要がある
年令が低ければ低いほど正しい技術や技能を身につけさせることが容易である。但し強制的にスポーツをやらせてはいけない。
低年齢からの一貫指導は一流のアスリート育成の絶対条件である。
●正しい教育とは
髙田 誠 は、本当の教育とは、ただ単に、何が正しいかを教えるのではなく、問題に直面した時,瞬時に現状を認知し,今なすべき事は
『何が正しいかを見分ける能力と知恵を身につけさせる』ことだと考えている。 これは一般の社会生活の上でも大変重要なことと考えている。
例 レーン・コンディションの読み レーンの攻め方
ストライクの科学 レスポンス・タイム ボールの選択
●コーチのための ジュニア育成の基礎知識
* すべてのジュニアはアスリートとしての大きな可能性を持っている。
スタートが早いか遅いかで、到達レベルが決定づけられる。
* 基本はスタート時点でタタキコメ。基本は後々では指導できない。
* 世界レベルのアスリート育成は3歳からスタートしたい。
* 世界レベルのアスリート育成が成功するための条件バランスは、
スタートの年齢 30% コーチの能力 30%
本人の能力と努力 20% 家族のバックアップと 練習環境 20%
* 世界レベルのジュニア育成は一貫指導システムでなければならない。
* 初めての指導・初めてのボールでジュニアの将来が決まる。
* ジュニアが使用するハウスボール・オーナーボールの留意点。
* ハウスボールのピッチとスパンをチェックする必要性あり。
* 基本のフォーム作りにはコンベンショナルグリップの活用を考える。
* 世界レベルアスリートの基本的フォーム作りは15歳までに完成すべし。
* ジュニアの骨格作りと基礎体力作りは親の責任。計画的食事内容。
* 間違ったトレーニングは、やればやるほど下手になり障害を起こし易い。
* 頭脳が本当に理解しなければ、身体は反応しない。
《 スポーツとは、心が身体を支配すること 》
* 体力不足のアスリートに集中力など有ろうはずがない。先ず体力増強。
* スポーツ技能を高めよう。
* 投球技術の指導は疲れるまでやるな、疲れると他の筋肉を使いスランプ
の原因となる。
●スポーツ指導の一貫性
【効果的な地域スポーツクラブにおける継続的一貫指導】
日本の学校体育は、小学校⇒中学⇒高校⇒大学⇒社会人⇒プロ と年齢的成長をする毎に、監督やコーチが変わる為に、同じコーチからの一貫指導が受けられず、進級する毎に異なったトレーニングを初めからやり直さなければならないと云う大きな矛盾があった。
スポーツ先進国アメリカや東ドイツでは、子供の時から、クラブスポーツを中心にした継続的な一貫指導がおこなわれている。
日本でも、水泳・体操・柔道・サッかーなどか次第にクラブスポーツの形態
をなし、継続的一貫指導に近づいて来ている。
アスリート コーチ
北島 康介 ⇔ 平井 伯昌 14歳からプロジェクトチームが指導
松田 丈志 ⇔ 久世由美子 4歳からボランティアのママさんコーチ
寺田 健 ⇔ 馬淵 崇英 19年間 中国のプロコーチ 飛込み
浜口 京子 ⇔ レスリング アニマル浜口 親 子
錦 織 圭 ⇔ テ ニ ス アメリカのプロ育成スクール
石 川 遼 ⇔ ゴ ル フ 父親の英才教育
宮 里 藍 ⇔ ゴ ル フ 父親と家族ぐるみの英才教育
●慕われ尊敬されるコーチ
◇ コーチは先ず 『ほめる』 事からスタートしよう。
従来、日本の体育会系の指導者には、選手やコーチがが今までやろうとして来たことを『そんなんじゃダメだよ!!』 と否定することからスタートする指導者が多かった。事実、否定しなければならないことがあったとしても、指導のスタートにおいては,何処かにその選手の長所を見いだして、褒めることからスタートする方が、指導される側の選手のヤルキを引き出し易い。
『選手が指導者の言うことを聞かないのではなく、
指導者に説得力がないのである』
すべてのボウラーに愛されることは難しいが、ジュニアに対しては慕われるコーチでありたい。
●指導者は 逃げてはならない
勝手気ままにやらせる事と個性を活かす事とはまったく違う。
ジュニアに対して『 自分で考えろ!!』 と発言する指導者は、指導者自身が、どうしてよいか解からないから逃げているのである。
指導者自身の学習不足・準備不足・能力不足・経験不足・情報不足に他ならない。
『無責任極まりないダメコーチはジュニアの素質を破壊してしまう』
●コーチは忍耐力の要る仕事だ
ジュニア指導者は、ジュニア本人が何故そうしなければならないのか、どうすればそれが出来るのかを本当に理解し、身体が理想的な反応をするまで、忍耐強く待たなければならない。
『コーチとは忍耐力が勝負の仕事だ』
●学ぶことを止めたコーチは教える事を止めなければならない
【古い先入観での指導は選手の足を引っ張る】
レーン素材が変わり、それにつれてボールが進歩し、そのボールを効率
よく投球するための投球技能とコーチング技法が日進月歩している。
この新しい情報を100%理解し、マスターしアスリートそれぞれの能力レベ
ル別に指導が出来なければ指導者としての資格はない。
●指導者しか選手を変えることが出来ない
【一流選手はフォームを変えられる】
こんな言葉があるが、これが出来るのは完成された超一流の選手であっ
て、一般的にはジュニア自身はどういうふうに変えたらよいのか、どうすれば
変えられるのかが判らないため、コーチのバックアップが必要となる。
●自己流コーチから一流コーチへ CHANGE
【コーチは自分自身を変えることが出来なければならない】
世の中には
* 変えたくても変えられない事
* 変えてはいけない事
* 変わらなければならない事 がある
●コーチが指導すべき スポーツ技能
【スポーツ技能のトレーニングと指導】
スポーツ技能 = スピード × 正確さ × フォーム × 適応力
スポーツ技能 ⇒ 日本に於けるスポーツ指導は技術中心が多かった。
≪技能≫と云う用語は、しばしば≪技術≫という言葉と同義語として使われがちであるが、技能には、ある環境条件を的確に判断認知し、そこで得られたさまざまな情報に基づいて決定を下し、さらにそれを運動化するといった人間の反応プロセス全体が含まれており、この≪全プロセスの巧みさ≫がスポ
ーツ技能であると言えよう。
スポーツ技術 ⇒ スポーツ技術とは、ただ単に最適な動作の形成や形態を意味するものであり、技能のようにプレイヤーの内面的なプロセスはふくまれていない。
●教えることの難しさ
【ボウリングのスポーツ性】
従来は、必ずしも肉体を鍛え上げなくても好成績が望めるのがボウリングのイメージであったが、最近は違う。ゴルフのタイガーウッズや野球のイチローやボウリングのショーン・ラッシュやブラッド・アンジェロの強さがそれを証明している。鍛え抜いたアスリートでなければ世界に通用する優れたプレイヤーに育てる事は出来ないことをコーチは知るべきである。
アスリートの肉体は 鍛えれば強くなる
鍛えすぎれば故障する
鍛えなければ弱くなる
【脳みそも筋肉と同じ】
ボウリングと云うスポーツは、反射神経にたよって戦うより、環境条件認知やスコアーメイク、ボールの選択など、ゲームの組み立てに比較的頭脳を使うスポーツ。 『 脳みそも筋肉と同じ、鍛えなければ弱くなる 』
【ボウリング上達への近道はない】
* 楽しくなければスポーツではない DIS-PORT
* サボル奴ほど上手くなる サボリは究極的合理化論
* 素晴らしいコーチ 正しいトレーニング・プログラム
* 優秀なプロショプ・スペシャリスト 正しいボール・正しいシューズ
* 優秀なテクニカル・サポーター 勝つ為のノウハウのサポート
* 良きトレーニング環境 レーンコンディションと練習仲間
* 自己管理能力の指導 目標設定、我慢と努力
* メンタル面での体験的指導 集中力(体力)とアガリ
* プラトー現象を乗り越える 正しい知識・本物の情報
【コーチの仕事】
* コーチは『 コイツはモットできるんだ 』と信じる事からスタートせよ。
* コーチの仕事で重要な事は、選手に『 夢と想像力を持たせる 』事である。
* コーチは『 冷静にして、熱く燃えろ 』
* コーチの『 ひたむきさ 』は選手を奮い立たせる。
* 選手がついて来るかどうかは、『 コーチが苦しんだ量に比例する 』
* 選手に昨日と今日の『 上達過程を認知 』させられなければ、練習意欲を持続させることはできない。
* ボウラーが惚れるコーチたれ。
* コーチはむやみやたらに教えるよりも、選手の好不調をじっくり観察せよ。
* 思いつき指導はダメ、指導には十分な準備が必要
10分間話すには最低でも30分の準備が必要。
* 具体的にマスターできる『 目 標 』を持たせよ。 髙田方式 ENDEAVOR
野球の例
打つ 1) トスバッティング バットの芯でボールを捕らえる
2) 狙った方向に飛ばす 上下左右
3) 遠くに 速い 強い打球を
守る 1) すばやくボールのコースへ近づく 《イチロー談話》
2) 正確に補給する 次の投球動作に入り易い姿勢で
3) すばやく正確に速い直球を送球する 内野手の例
* 選手が勝った時にこそ、しかることの出来るコーチになれ。
* 何故そうした方が良いのか、どうすればそう出来るかを理解させよ。
* 技術指導でジュニアが素直にコーチの話に耳を傾けてくれるのは一度に
3分間が限度。
* 身長の低い子供や視力の弱い子供にスパットは見えていない。
* 初めての子供に専門用語は禁句 スパット・・? レーン・・・?
イン・・・? アウト・・・?
●情報過多は 考える力 を消滅させてしまう
日本のボウリング業界には、あまり正確とは言えないような、ボウリング理論やボールに関しての情報が氾濫している。全てではないとしても、その殆どが実験データーに基づくものではなく、コンピューター上て作られた数値であったり画像であったり、机上の空論の場合がかなり見受けられる。
人間は、耳に入ってくる情報が多すぎると、情報までに行き着くプロセスが無くなるために考える力や考える習慣を失ってしまう。
従って、情報の寄せ集めでボウリング理論の展開や指導をする人の話には、よくよく聞いてみると矛盾点が多い。
ゴムボール時代や、600シリーズで勝てた時代の、昔からの思い込みで指導してはならない。
リリースの仕方、ボールの知識、ドリルの知識も他ならない。
《余談》
情報過多の時代到来は、生活の上では間違いなく便利にはなったとしても、間違いなく人間に考える習慣や力を減少させていることを私は危惧している。
こう考えると、スマート・フォンやアイ・パッド・タブレットなどの便利グッズの普及もジュニア達の将来を考えると多くの問題を抱えていると云わざるを得ない。
この問題を、我々大人に置き換えて考えてみると、パソコン等の普及で、もう既に漢字は読めても、難解な漢字を正確に書くことが出来なくなってしまっている。
漢字が読めない。漢字を正確に書けない。正しい日本語が話せない。
本を熟読する習慣がなくなった。
これでいいのかな~ ・・・・・・ 髙田 誠の独り言です。
過去の独り言はこちらから