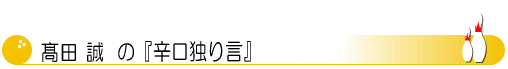
【コーチになぜ心理学が必要なのか】
スポーツを行うのは人間である。人間は他の動物と同様に、肉体を持った生物学的存在であるが、同時に高い水準の心を持つ心理学的存在でもある。
したがって、スポーツという活動を理解し、これを効果的に実施して行くためには、ただ単に生物学的側面のみならず、人間としての心理現象についての配慮がなされる必要がある。根性だけで勝てる時代ではない。
【学習の心理学的法則】
勝つ為には必然的に技能の向上を求める傾向が強くなる。これは練習によって成し遂げられるが、練習を効果的ならしめるには練習過程に於いて、学習の心理学的法則を上手く取り入れることが必要である。
その際、自分の動作をどのように知覚し、判断し、最終的に目的にかなった有効な動作を生み出すかと云う認知能力や、認知の法則の活用なども重要な問題である。正しく活用すれば映像やトレーニング機器の利用は大変有効である。
【年令による心理的特徴】
指導しようとするボウラーの年令的な心理的特徴を考慮しなければ適切な指導は行えない。小学生と中学生とでは心理的特徴は大きく異なっているし、高校生と成人とでは大きくその性格は異なっている。
【ボウリング特有の心理的問題点】
ボウリングに於ける投球は、弓道やライフル射撃と同じく標的を狙って静的な意志動作を集中して行う動作であり、サッカーやラグビーや野球などの対戦ゲームやフォーメーションゲームとは異なる。
【性格的特徴】
引っ込みがちな子、積極的で明るい子、闘争心旺盛な子、見栄っ張りな子、頭脳明晰な子、恥ずかしがりやな子、要領の良い子、のみ込みの早い子、理解に時間のかかる子等などその性格は10人10色である。これらの条件を全て理解した上で指導するのでなければ、指導の成功を期待するのは難しい。
したがって、一度に多くの人数を担当することは成功の確率を低くする。
【年令的特徴】
小学生 → 知的な面での特徴は日毎に記憶力の向上。
成 人 → 中高年の記憶力は加齢ととも急速に低下をたどる。
【感情や動作】
小学生 → 安定
高校生 → かなり不安定
成 人 → 保守的 一度覚えた事柄にしがみつく
【社会面】
中学生 → 集団化は容易である
大学生 → 集団化はかなり困難
成 人 → 社会的地位によりまちまち
【運動面での発達】
小学生の段階では著明であるが、加齢と共に急激に薄れていく。
【コーチングのポイント】
コーチを受ける選手の発達段階の心理的特徴について充分理解し、彼らの心理的特徴に適合したコーチのボイントを把握することが大切である。
【コーチングの一貫性】
本格的アスリート育成は、指導テクニック・指導内容・指導目的・指導環境など、その全てに一貫性がなければ世界的アスリートは育てられない。
思いつきで行うその場限りの無責任なアドヴィスはジュニアを混乱させる。
【練習時の心理学的問題】
練習に関する心理学的問題の第一は動機づけである。動機づけが適切に行われて、達成動機のレベルが充分に高められれば、コーチとしての仕事の60%は達成出来たと考えてよい。そのためにはどのような方法が動機づけとして効果的であるかをコーチは知っておかなければならない。
【プラトー現象とスランプ】
練習によって向上する技能の過程は、常に単純に右肩上がりに向上するとはかぎらない。それは、練習しようとする事の内容や、練習しようとする選手の体力や性格などが反映していて、必ずしも一本調子で上達するものではない。
技能が、あるレベルに達するとそれ以上は容易にスコアーアップしなくなるプラトーと云う現象がやってくる。時には本当のスランブに陥ることもある。
練習過程でよく見られるこのような時期を、いかにして上手に乗り越えさせるかはコーチにとって大変大きな課題である。
【試合を意識した練習】
試合に勝つ為には、日頃からの絶えざる体力トレーニングとこれを支える食事メニュー、及び技能練習が絶対的に必要である。
しかし如何にハードなトレーニングに耐え、技能を高めたとしても、試合中のある瞬間に突如として不安感に襲われたり、迷いが生じたり、焦ったりすれば、次の瞬間に自滅してしまう事が少なくない。
ボウリング競技において勝敗の鍵を握っているのは、まさに集中力にほかならない。このような事態に関わらず、試合で全力が発揮できるようにする為には、平素から心理的コンディションを上手く調節できる能力と、疲れない体力づくりを指導して行かなければならない。
●北島康介と5人の鬼たち
国立スポーツ科学センターの設立により、種目別毎のプロジェクトチームが結成され科学的トレーニングが可能になってきた。
金 メダルチーム
平井伯昌 ⇒ 総合コーチ
河合正治 ⇒ 映像分析
岩原文彦 ⇒ 戦略分析
田村尚之 ⇒ 肉体改造
小沢邦彦 ⇒ コンディショニング
●目は情報認知の入口
【競技の目】 自分の距離を作る。
アプローチの上手下手で体力を補うことができる。
【見 る 目】 一般視力 動体視力 瞬間視力
【観 る 眼】 認知力 観察力
間接視力 → この辺りにボールが飛んできそうだと予測する眼
このくらい曲がりそうだと予測する能力
【レーンコンディションの変化を観る眼】
【観察の仕方を学ばせる】
【視点の置き方を学ばせる】
●コーチングの視点
【観察の仕方を指導する】
【観る力は戦術的能力の重要ファクター】
観ると見るとの違いを指導する。観る力はトレーニングでマスターできる。
●観る眼のトレーニング
【眼がよい選手】
スポーツでは、眼が良いという意味は ⇒ 状況判断が良い選手のこと
野球におけるバッティングも、ボウリングにおけるレーンコンディションのヨミも状況判断である。
1.どうなっている ⇒ 知覚的要素
2.どうすれば良いか ⇒ 戦術的要素
●スポーツと眼
【追跡系スボーツ】
野球 テニス 卓球 バトミントン 動態視力は横方向
【視野系スポーツ】
サッカー バレー バスケット ラグビー 認知力
◎これらのスポーツは、間接視力が大切
【クローズド・スキル系】
ボウリング 水泳 陸上競技 ハンマー投げ 観察力
◎競技レベルが高いほどスポーツビジョンも高度になる傾向がある。
●眼のビジュアルトレーニング
【競技の眼の体力アップ】
動態視力 眼球 周辺視野 瞬間視力 間接視力をアップする
◎屈折矯正手術 オルソケラトロジー JISS 眼科外来
●ボウリングとリンクした種目的なトレーニング
・情報 ⇒ 眼から
・処理決定 ⇒ 脳
・実行 ⇒ 身体
●前頭前野の活性化
【目から入った情報は前頭前野に伝わる】
知覚 ⇒ 分析 ⇒ 判断 ⇒ 決断 ⇒ 実行
これをシステムとして使えるかどうかがレーンコンディションの読みにつながる。ここでスポーツ技能の優劣が、アスリートのレベルを決定する。
●健康な歯の大切さ
【奥歯はパワーの根源】
子供のときから予防歯科を活用 3ヶ月に一度はチェック
●ドーピングの注意
【親にドーピングの厳しさを指導する】
過去の独り言はこちらから